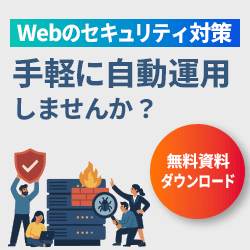WebアプリにはWAFと脆弱性診断どちらも必要?役割の違いや重要性を解説

Webアプリケーションのセキュリティ対策で「WAFさえあれば十分」「脆弱性診断は年1回でいい」と考えていませんか?
本記事では、WAF、脆弱性診断の役割と限界、規制対応まで含めた最適な組み合わせ方を解説します。これを読むことで、自社システムを持続的に守る具体的な導入・運用ステップがわかります。さらに、費用対効果を数値で示すことで経営層の了承を得るヒントも得られるでしょう。
AWS、CloudflareのWAF運用をもっと楽に!
WAFの自動運用サービス WAFエイド
目次
WAFと脆弱性診断の基礎知識
WAFとは
Web Application Firewall(WAF)は、Webアプリに対して接続しようとする通信をリアルタイム検査し、不正アクセスを即時遮断する防御装置です。SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングといった代表的なサイバー攻撃を「シグネチャ」という既知の攻撃パターンを定義したルールに基づいて検知するシグネチャ型と、通常トラフィックの振る舞いを学習して異常を検出する振る舞い監視型があります。
クラウド型サービスなら数クリックで簡単に導入でき、CDN 一体型 SaaS、オンプレミス用アプライアンス、コンテナ型など形式も多彩です。
最大のメリットは「常時監視しながら即時ブロックまたは検知できる」という運用性で、本番環境を24時間ガードレールで守るイメージです。近年はAPIを対象とした専用のWAFや、機械学習ベースで検知を行う製品も登場し、多様化するサイバー攻撃に合わせて進化を続けています。
関連記事:WAFとは?セキュリティ対策の必要性や仕組みを解説
脆弱性診断とは
脆弱性診断は、システムに潜む弱点を公開前または運用中に洗い出す評価プロセスです。外部から攻撃者になり切って確認するブラックボックス方式、ソースコードや設定情報を用いて内部視点で検査するホワイトボックス方式が代表例となっています。
実行手法は、スキャナで広範にチェックする自動ツールと、専門家が手動で攻撃シナリオを試すペネトレーションテストの組み合わせで、脆弱性を網羅的に検出します。対象は Webアプリだけでなく API、モバイルアプリ、クラウドに関する設定、OSSベースのミドルウェアまで多岐にわたり、診断報告書は修正優先度や再診断指標の指針となります。
最近はアプリケーションを継続的に改善・開発するCI/CDに脆弱性診断を組み込むDevSecOpsも流行してきています。
関連記事:脆弱性診断(セキュリティ診断)とは?必要性など基礎から解説
共通点と相違点とは?
WAFと脆弱性診断はどちらも「サイバー攻撃からシステムを守る」点で共通しますが、立ち位置は大きく異なります。WAF は交通警備員のように入口で全リクエストをチェックし、怪しい動きをリアルタイムにブロックする“守りの継続監視”です。
脆弱性診断は健康診断に似ており、一定期間ごとにシステム全体を検査して潜在的な問題を洗い出す“攻めの棚卸し”です。
両者を組み合わせれば「未検知の脆弱性が攻撃されてもWAFが一次遮断」「WAFが対応しきれない論理的欠陥を診断で早期発見」という相互補完が成立し、運用しているアプリケーションにおいて十分なセキュリティ対策が実装できます。
また、診断報告→修正→WAFルール最適化のサイクルを回すことで、未知の脅威にも強いセキュリティ運用体制を整備することができます。
WAF運用に手が回らずお困りの方へ WAFエイド

・WAFの最適な設定ができているか分からない
・WAF運用に手間がかかっている
等のお悩みはありませんか?WAFエイドによる自動運用と専門家の知見で解決します。
WAFと脆弱性診断、なぜ両方必要なのか
診断だけでは守り切れない“運用ギャップ”
脆弱性診断は“点検”であり、検査と検査の間はノーガードです。本番公開後に急増するBotスクレイピングやログイン試行のクレデンシャルスタッフィングは、診断翌日から始まることも珍しくありません。診断間隔を月次→週次などと短縮すると費用と担当者負荷が跳ね上がり、現実的ではないのが実情です。
また、修正しても次のリリースで再発する“リグレッション”も起こり得るため、運用フェーズで継続防御と可視化を行うWAFが欠かせません。
規制、ガイドライン対応における必要性も
多くの業界基準は“継続的防御”と“定期的評価”の双方を要求します。
たとえばクレジットカード業界におけるセキュリティ基準である、PCI DSS v4.0では、「Webアプリの防御として WAF等を導入し、年4回以上の脆弱性スキャンを実施すること」と明記されています。
国際的セキュリティ基準であるISO-27001 や、経産省『サイバーセキュリティ経営ガイドライン』も同様に、運用中の監視ロジックと計画的な脆弱性評価をセットで求めています。
片方だけでは監査指摘を受け、最悪の場合は取引停止・是正勧告につながるリスクがあります。特に金融・決済系では準拠有無がサービス継続の前提条件です。
双方向カバーで得られる効果
WAFと脆弱性診断を組み合わせると、セキュリティは“点”から“線”、さらに“面”へと広がります。
高速道路と車の定期点検に例えると、WAFは道路脇のガードレールと速度監視カメラで事故(攻撃)を未然に防ぎ、脆弱性診断は車両点検でタイヤの摩耗やブレーキのゆるみ(潜在欠陥)を事前に発見して修理計画を立てる役目と考えていいでしょう。
両方を実施すると、
未知の脆弱性が露呈→WAFが一次ブロック→診断で原因究明→ルールとコードの両面を改善
という好循環が生まれ、セキュリティインシデント発生時のMTTR(平均復旧時間)が短縮します。WAFの検知ログを診断チームに共有すれば高リスク箇所を重点的に再診断でき、逆に診断結果を WAF にフィードバックしてシグネチャを先回り補強できるため、限られた予算でも“守りと攻めのバランスが取れた”セキュリティ態勢を維持できます。
WAFと脆弱性診断を導入していくには?
現状の把握
導入前に行うべきは “何を守り、何が狙われるか” の棚卸しです。
- 資産管理台帳を更新する
例えば運用しているシステムを一覧化します。その中で、利用しているドメイン名、APIエンドポイント、など、外部に公開しているIT資産を一覧化します。 - 脅威モデルを描く
「SQLインジェクション→個人情報漏えい」「Bot→価格改ざん」など攻撃パスを矢印で可視化すると、非技術部門にも伝わりやすくなります。 - 攻撃面(Attack Surface)の測定
ZAP や Nmapといったツールを利用し、自社で利用しているIPアドレスレンジをスキャンし“入口”を数値化します。専門のベンダーに依頼してもいいでしょう。 - 診断実績の確認
直近の脆弱性診断レポートの有無や、再診断サイクルの把握をします。 - 年間被害想定コストを試算
たとえば「漏えい1 件あたり平均2万円✕10万件=2億円」。これをWAF+診断年間コストと比較すれば ROIが出しやすくなります。
セキュリティ対策は費用対効果の説明が難しいですが、参考値として算出するだけでも、経営層の合意が取りやすくなります。
運用体制の確立
技術対策と同時に “誰がWAFや脆弱性診断の結果アラートを見るのか” を決めなければ形骸化します。具体的には以下のようなことを決めるといいでしょう。
- 責任分担表(RACI) を作成し、WAF アラート一次対応=運用チーム、重大インシデント=CSIRT など、役割を明確化します。
- プレイブックを用意し、「WAFがSQLインジェクションをブロック→日次などでにDBログ確認→週次でブロック件数を報告」と時系列で手順を書くと迷わないでしょう。また、定期的に訓練を行うと運用が定着します。
- 診断スケジュール は開発リリースと連動させ、「機能追加ごとに軽量スキャン、四半期ごとに総合診断」とカレンダーへ登録します。これらをSOCツールや メール、Slack、Microsoft Teams チャンネルで自動通知させれば、担当者が交代しても継続的に回せます。
WAF導入の流れ
WAFの導入順序を追っていきましょう。
1. PoC(概念実証)
30日間トライアルで「検知率」「誤検知率」を計測。既存ログと突き合わせると効果がわかりやすいです。
2. ミラーモード
本番トラフィックを監視のみで通し、誤検知ルールを洗い出しすることで、誤検知のリスクを極小化できます。また、まず SQLインジェクションやXSSなど高リスクなサイバー攻撃だけブロックし、安定後にその他の攻撃をブロックすることも検討します。
3. 関係部署レビュー
誤検知で業務が止まらないよう、ステークホルダーやユーザーテストを実施してから全面切替を行います。
WAFの継続的運用の確立
導入後は “回し続ける仕組み”が重要です。
- 運用状況の可視化
ダッシュボードでWAF検知件数・ブロック率・診断検出件数を毎週確認し、誤検知率やクレーム件数などをKPIとして掲示します。 - 自動ルール更新(脅威インテリジェンス連携)
定期診断を自動化することで、属人化を低減します。 - チューニングサイクル
重大インシデント抽出→再診断→新ルール追加といったサイクルを回すようにします。 - 教育と共有
「今月の攻撃トレンド」などの勉強会を定期的に開き、非技術部門に必要に応じて参加してもらいます。
【資料】登録不要で今すぐ見られる!AWS WAF運用を楽にする最適な自動化の進め方
この計測→改善→学習を回し続けることで、WAFと脆弱性診断の投資効果を長期にわたり最大化できます。
登録不要で公開中!AWS WAFの誤検知対策を解説
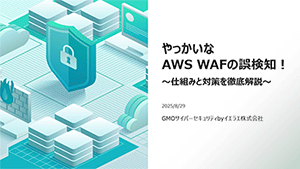
AWS WAFにおける誤検知の要因と、それを減らすための運用改善のポイントを解説します。
登録不要!今すぐ資料を見る脆弱性診断実施の流れ
ここでは、脆弱性診断を実施する際の流れを解説します。
1.診断対象、範囲を決定
対象がWebアプリケーションであれば、対象URLや機能一覧、画面数、APIの有無を整理します。基盤やネットワーク診断を含める場合は、対象IPアドレス、サーバー台数、ネットワーク機器の種類も明記します。
併せて、本番環境か検証環境かを事前に決めておくことも重要です。範囲設定が曖昧だと見積もりやスケジュールに影響するだけでなく、重要な箇所の診断漏れにつながります。
2.社内またはセキュリティベンダーへ依頼するかを検討
診断の実施方法を決定します。社内実施の場合は、脆弱性診断ツールの導入や運用ルールの整備が必要です。短期間で何度も診断できる利点がありますが、診断精度は社内の知見に依存します。
ベンダー依頼の場合は、手動診断を含めた高精度の検査や、最新の脅威動向に基づくアドバイスを受けられる利点がありますが、実施のたびに費用と日程調整が必要です。
3.診断実施後、検出されたリスクを修正する
診断が完了すると、検出された脆弱性とその重要度がレポートとして提示されます。
レポートには、脆弱性の内容、再現手順、影響範囲、推奨される修正方法が記載されているのが一般的です。
修正後は、必要に応じて再診断を行い、問題が完全に解消されたことを確認します。
4.定期的な診断の実施
脆弱性診断は一度きりでは効果が限定的です。
新たな脅威や脆弱性は日々増加しており、システムの安全性は時間とともに低下します。そのため、システムの改修やソフトウェアのアップデート、インフラ構成変更などのタイミングでも診断を実施すると、リスク低減効果が高まります。
WAFと脆弱性診断、役割をそれぞれ抑えておくことで、より強固なセキュリティ対策が可能になります。
脆弱性診断の選び方・進め方を更に詳しく解説

なぜ脆弱性診断が必要なのか?どのように手法を選べばいいのか?といった疑問をお持ちの方へ向けて、その理由や方法を解説する資料です。
資料ダウンロード監修:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ 編集部

企業の情報セキュリティ担当者や開発者向けに、サイバーセキュリティに関する情報を発信しています。